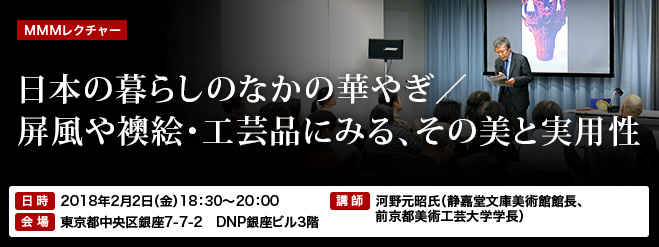現在MMMで開催中の「屏風特集」(〜3/20)にちなみ、2月2日にレクチャーが行われました。講師にお招きしたのは、琳派誕生400年記念の2015年、琳派についてたっぷりお話しいただいた河野元昭先生。今回は、「日本の暮らしのなかの華やぎ」をテーマに、日本の美の魅力を語っていただきました。
午前中まで雪が降っていた寒い日にもかかわらず、琳派研究の第一人者の河野先生のレクチャーとあって、多くの参加者の方が駆けつけてくださいました。
「日本は美の国です。厳密にいうと、日本は生活に美が根付いた国であるといって間違いではないと思います。今日はそのような観点から、日本の美の歴史についてお話ししたいと参上しました」と、“饒舌館長”河野先生のこうした言葉からレクチャーが始まりました。

西洋において芸術は、「建築」「彫刻」「絵画」「工芸」という順に序列がありますが、「日本にはこうした“ヒエラルキー”はなく、すべてひとつの美として認識されてきました」と河野先生。さらに美術という言葉も明治時代になってから誕生したと言います。その理由について、「素晴らしい美が生活のなかに溢れすぎていて、ひとつにまとめる概念的な言葉がなかったと私は認識しています。そして近代になって日本は洋式化していきますが、そのなかで日本の美の伝統は、受け継がれていったのです」と明かしてくださいました。

続いて、日本の美を象徴する“河野先生のベスト10”をスライドを交えながら紹介。最初は縄文時代の「火焔土器」。「いわば鍋、釜であったものに、このような見事な装飾を施してきたのが日本人の美意識の原点にあります」。
「平安時代の後期は日本の独自の文化が生まれた時代で、屏風が愛好されたのもこの頃のことです。屏風は風を防ぐ家具であり、その屏風に大和絵を描いて生活を豊かにしました。さらに、屏風歌といって、屏風を見ながら和歌を詠んだり和歌をつくったりした。絵画と文学が不即不離の関係にあり、さらに生活を豊かにするものとして存在していたのです」。
一方、西洋人は近代になってから自分なりに絵を解釈し、その絵のなかに自分を没入して楽しむ「感情移入」と呼ばれる鑑賞法を編み出したそうで、文明の点では日本の方が“後進”だったにもかかわらず、美への考え方については“先進”だったことに驚きました。
さらに時代は下って、江戸琳派の創始者、酒井抱一の《十二か月花鳥図》について話は進んでいきます。 「この掛け軸は、今でいうと純粋美術に属するもので、1月から12月までの一種の連作になっています。おそらくお客さんが来た時に、その季節にふさわしいものを掛けて楽しんだのでしょう。たとえば、ルーヴル美術館の油絵は、基本的にいつ行っても同じものが飾られていますが、日本の美術館ではそのようなことは絶対にありません。それは日本の絵画が原材料の問題もあり退色しやすくか弱いこともありますが、同時に季節ごとに掛けかえることには、美術が生活と、とりわけ季節と結びついている伝統が、そしてDNAがあるからだと私は思います」。

また、美術としても絵画としても評価されていなかったという大津絵《鬼の邪念》についても解説。この作品に新しい美を見出したのは、大正時代に民藝運動を起こした柳宋悦だったと言います。「柳宋悦は、本当の美は民衆がつくり出したモノのなかにこそ存在すると言い、民藝という名をつけて美術のひとつのジャンルとして確立させました。彼がそのなかで挙げたのは、無名性、廉価性、そして多量性で、生活のなかで使われるためには、安くて多く存在することが必要と謳った。それこそが民藝であり、絵画でいえば大津絵だったといっていいでしょう。そして大津絵のなかには、日本の美が脈々と生きているといってよいと思います」。
時折、冗談を交えながらの歯切れのよいトークで、日本の生活の美について丁寧にお話ししてくださった河野先生。先人たちの考えに触れ、日本古来連綿と続く生活のなかの美の魅力を再認識したレクチャーとなりました。
[FIN]