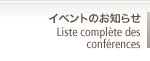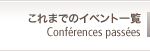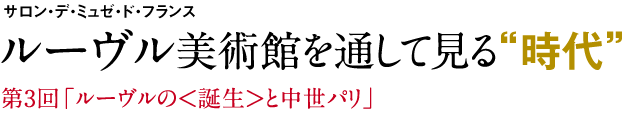
ルーヴル美術館の所蔵品を通じて、古代から近代までのそれぞれの時代を見る全4回の連続講座。3月のテーマは、「ルーヴル美術館を通して見る<中世>と<近代>」です。第3回は美術館となる前のルーヴルと中世のパリの姿を、中央大学文学部教授の杉崎先生にお話いただきました。
 「さて、ルーヴル美術館といえば、ガラスのピラミッドがもうお馴染みとなりましたが、今回はそのピラミッドができるずっと以前の中世の時代を、皆さんと一緒にヴァーチャルに旅をしていきたいと思います」。明快な口調でこう切り出された杉崎先生。スライドにはまずルーヴル美術館の鳥瞰図が映し出されました。広大なルーヴルの建物のどの部分が、いつ頃に造られたかがひと目で分かる鳥瞰図です。「この図をご覧いただいてもお分かりの通り、じつはルーヴルは中世の時代には影も形もなかったのです。ルーヴルでもっとも古い部分は、現在クールカレーと呼ばれる一角。そこも16世紀、フランソワ1世の時代に建造されたものなので、中世の時代とはいえません。ではこれから、現在のパリから時代を遡ってみましょう」。スライドに映し出されるパリの写真や資料とともに、杉崎先生を案内人として、パリの中世への“時間旅行”が始まりました。
「さて、ルーヴル美術館といえば、ガラスのピラミッドがもうお馴染みとなりましたが、今回はそのピラミッドができるずっと以前の中世の時代を、皆さんと一緒にヴァーチャルに旅をしていきたいと思います」。明快な口調でこう切り出された杉崎先生。スライドにはまずルーヴル美術館の鳥瞰図が映し出されました。広大なルーヴルの建物のどの部分が、いつ頃に造られたかがひと目で分かる鳥瞰図です。「この図をご覧いただいてもお分かりの通り、じつはルーヴルは中世の時代には影も形もなかったのです。ルーヴルでもっとも古い部分は、現在クールカレーと呼ばれる一角。そこも16世紀、フランソワ1世の時代に建造されたものなので、中世の時代とはいえません。ではこれから、現在のパリから時代を遡ってみましょう」。スライドに映し出されるパリの写真や資料とともに、杉崎先生を案内人として、パリの中世への“時間旅行”が始まりました。ルーヴルが美術館として市民に開放されたのは、フランス革命中の1793年のこと。フランス王ルイ16世と王妃マリー=アントワネットが断頭台に消えた年のことでした。それまでパリの王宮だったルーヴルで、王家ゆかりのコレクションが展示されることになったのです。ではルーヴルが宮殿となったのはいつのことでしょう。それは1527年、フランソワ1世が経済的な理由からパリ市民に接近するためルーヴルを正式な王宮としたのが始まりです。フランソワ1世といえば、レオナルド・ダ・ヴィンチをフランスに招聘したことで名高い“文化王”ですが、現在ルーヴル美術館の至宝となっている『モナ・リザ』は、ダ・ヴィンチが最期まで手元に置いていた作品。画家の死後、パトロンだったフランソワ1世のコレクションに加わり、そして17世紀にルーヴルへ入ったものなのです。
「でもじつはこの前にもルーヴルはあったのです。宮殿というほどの規模のものではなく“館”というようなものでしたが……」と言いながら先生が見せてくれたスライドは、≪ベリー公のいとも麗しき時祷書≫に描かれた10月の場面。実りの秋を迎えた田園の背景に確かに“館”時代のルーヴルの姿を見つけることができました。「そしてルーヴルが建物として初めて登場したのは、1190年頃のことです。城砦としてここにルーヴルが産声を上げたことになります」。当時のヨーロッパのほとんどの都市は、街を守るための壁を持っていました。いまやパリの中心にあるルーヴルもその時はパリの城壁の外側に位置する砦だったのです。約800年の時を遡り、先生とともに中世のパリの街を、そしてルーヴルを巡った1時間半の旅。「次回パリを訪れる際には、ルーヴルはもちろん、街の片隅に中世の面影を探して歩く楽しみがひとつ増えました」との声が参加者の皆さんから上がりました。
さて、サロン講座のもうひとつの楽しみのティータイムで、供されたお菓子は、先生がこの日のために頭をひねって考えてくださった「ガレット」です。17世紀にフランスで出版されたぺロー童話集のなかに収録された『赤ずきん』の一節にも登場する「ガレット」をつまみながら、講座終了後のホワイエでも杉崎先生を囲んでの“時間旅行”は続いていました。