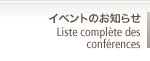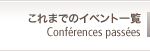3月28日から東京国立博物館で開催中の「Story of... カルティエ クリエイション〜めぐり逢う美の記憶」。世界的評価の高いデザイナー吉岡徳仁氏の監修のもと、“王の宝石商、宝石商の王”と称されるカルティエの作品とその歴史の物語が展観されています。今回のサロンでは本展の開催を記念して、カルティエ インターナショナル イメージ スタイル&ヘリテージディレクターのピエール・レネロ氏に、カルティエ作品とその歴史的背景をお話しいただきました。
 「カルティエの歴史は、ひと目見て他とは違うスタイル、つまりこれぞカルティエというスタイルを創り上げることを目指した歴史でもあります」
「カルティエの歴史は、ひと目見て他とは違うスタイル、つまりこれぞカルティエというスタイルを創り上げることを目指した歴史でもあります」揺るぎない哲学とカルティエへの深い愛情を感じさせる語り口で話し始めたピエール・レネロ氏。今回のサロン講座では、カルティエが多くの顧客たちと紡いできた歴史と、独自のスタイルをどのようにして育んできたかをお話いただき、さらには今回の展覧会の15分のメイキング映像をご覧いただきました。
「カルティエの歴史は1847年、宝石職人ルイ=フランソワ・カルティエとその息子アルフレッドによって幕を開けます。しかし19世紀末頃までは、現在のようなこれぞカルティエという独自のスタイルは、まだ誕生していませんでした。“宝飾界の革命”が起きるのは1898年、アルフレッドの息子、ルイが参加するようになってからのことです」
それまで、ジュエリーのデザイナーは工房付きであり、販売するブランドに専任デザイナーが入ることはなかったそうです。しかしルイは自らのブランドのためのデザイナーを確保し、さらにジュエリーにプラチナを使用することを決めました。これが当時の宝飾界にとっての大きな2つの革命になったのです。プラチナは非常に強い金属で劣化することがありません。また、しなやかでこまやかな細工が可能なため、動きのある新しいスタイルのジュエリーを作ることができました。そしてもうひとつ、ルイがプラチナにこだわった理由がありました。それは、照明の変化でした。この頃から電気が使用されるようになり、銀の台の上にセットされたそれまでのジュエリーは、電気のもとにさらされると、黒ずみ重い印象を与えてしまったのです。そんな問題を解決したのがプラチナでした。このエピソードからも分かるように、ジュエリーは社会や生活スタイル、さらには女性の生き方の変化をも色濃く映し出すものだったのです。
カルティエが創出してきたジュエリーや時計に込められた哲学やスタイルの変遷、またココ・シャネルやグレース・ケリーといった顧客とのエピソードをお話いただいた今回のサロン講座。ジュエリーの美しさだけでなく、その背後に脈々と流れるカルティエの珠玉の“ストーリー”を堪能できたひと時となりました。最後にレネロ氏が引用したジャン・コクトーの印象的な言葉をご紹介しておきましょう。
「カルティエはまさに魔術師だ。月を切り取って糸につなげ、太陽の輝きを与えるのだから」
展覧会場で“太陽の輝き”をこの目で確かめるのが楽しみなサロン講座となりました。