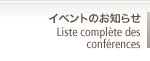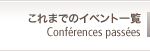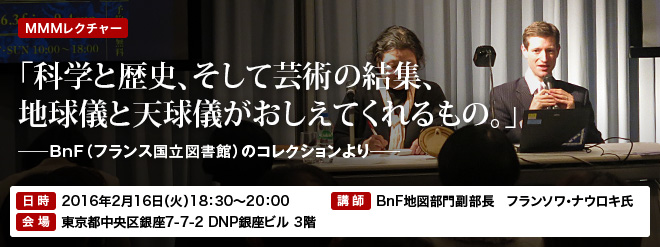2月19日よりDNP五反田ビルで「フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展」が開催中です(前期は〜5/22、後期は6/3〜9/4)。開幕を3日後に控えたこの日、MMMではフランス国立図書館(BnF)地図部門副部長のフランソワ・ナウロキ氏を講師にお招きし、球儀の歴史と芸術的側面から見た魅力についてお話いただきました。

フランス・パリのBnFは、書籍、印刷物はもちろん、版画、写真、地図、コイン、装飾品など、約4,000万点もの幅広いコレクションを有する世界屈指の図書館です。中でも地図部門では、ウィーンの地球儀博物館、グリニッジ天文台と並び、世界有数の地球儀・天球儀のコレクションを所蔵しており、その数200点以上にもおよびます。DNP大日本印刷では、世界各国で製作されたその作品群の中から、歴史的に貴重な55個を選定し、世界初の3Dデジタル化を実現。2月19日よりDNP五反田ビルで、前期・後期に分けて計10点の作品を特別展示しています。
「Bonjour! 展覧会を直前に控え、皆様の前でお話できることを嬉しく思います。今回のレクチャーでは地球儀・天球儀のコンセプトを理解していただきたいと思います。これらは、その当時の地球・天球観を表すと同時に科学的なツールでもありました。一方で、装飾品としても芸術的な価値を持っていました」というナウロキ氏の解説からMMMレクチャーは幕を開けました。
地球儀・天球儀の歴史は、古代ギリシア・ローマ時代にまで遡ります。しかし現在とは異なり、天球儀は「プトレマイオス型」、つまり地球を中心としたものでした。「現在は、地球が太陽の周りを回る星であることを誰もが知っていますが、かつては地球の周りを他の天球が回っていると考えられていました。しかし、16世紀に天文学者でもあるコペルニクスが地動説を唱えたことがきっかけとなり、プトレマイオス説が捨てられたのです。そして太陽を中心とした「コペルニクス型」に移り変わりました」。一方、地球儀はというと、15世紀末、コロンブスをはじめとする航海士によって世界の様相が明らかになってから作られ始めたといいます。

3Dデジタル化された作品画像の紹介をはじめ、絵画に描かれたモティーフとしての地球儀・天球儀が意味することなど、次々と披露されるお話は参加された皆さんの好奇心を刺激するものとなったようです。
「展覧会にお越しいただければ、地球儀・天球儀のあらゆる側面を発見することができるでしょう。今回、DNPと共同でさまざまなデジタルコンテンツを開発をしています。それを通して学び、さらに広く、深く考えることを目的にした、実に美しい展覧会となっています」。
フェルメールの《天文学者》(ルーヴル美術館所蔵)に描かれている天球儀や大航海時代の様子を示す16世紀の作品などが展示される「フランス国立図書館 体感する地球儀・天球儀展」。デジタル技術を駆使し、新しい作品の見方を提案する展覧会に、ぜひ足をお運びください。
[FIN]