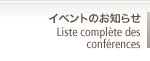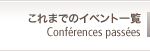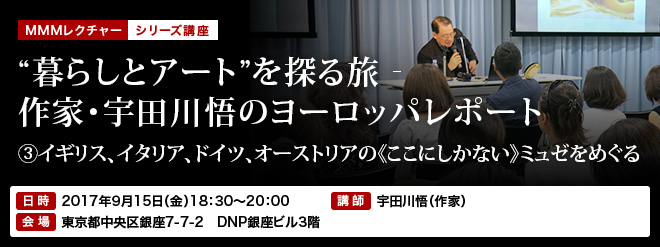フランス・パリに20年以上生活し、世界の文化にも造詣が深い作家・宇田川悟氏が、ヨーロッパ各地のミュゼとその土地の暮らしや文化について紹介するシリーズ講座「“暮らしとアート”を探る旅」。9月15日、その第三弾講座が開催されました。今回はイギリス、イタリア、ドイツ、オーストリアの“ここでしか見ることができない”ミュゼをテーマにお話しいただきました。
宇田川氏の講座はこれまで、フランスのミュゼを中心にご紹介いただきましたが、最終回となる本講座ではイギリス、イタリア、ドイツ、オーストリアの珍しいミュゼについてお話しいただくことになりました。
「一昨年まで、美術館・博物館の入館者数の世界一位がルーヴル美術館でしたが、2016年度はどこだか皆さんお分かりになりますか?」
講座冒頭、宇田川氏が参加者の皆さんに質問を投げかけます。悩まれている様子の皆さんの前で、「美術館・博物館の入場者数を研究しているある団体の報告によりますと、昨年、中国・北京の中国国家博物館がルーヴルに取って代わりました。2位はアメリカ・ワシントンの国立航空宇宙博物館、ルーヴルは3位となりました」と解答すると、会場からも驚きの声が上がりました。そんななかイギリスは健闘しており、大英博物館やナショナル・ギャラリー、テート・モダンがトップテンにランクインしているそうです。まずは躍進中のイギリスからフロイト博物館とナイチンゲール博物館を紹介してくださいました。

精神分析の創始者として知られるジークムント・フロイトは、チェコ生まれのユダヤ人。「無意識という未知の世界を発見し、理論付けるだけでなく実践に移しました。フロイトがいなかったら、夢の世界や無意識の世界は解明できていなかったと言っていいほど人類にとって非常に大きい存在です」と宇田川氏は話します。47年もの間ウイーンに住んでいましたが、ナチスの台頭により82歳でロンドンに亡命。その理由を「好きな作家がシェイクスピアで、敬愛する学者がダーウィンだったからということと、生まれた地と景色が似ているからという理由もあったようです。ロンドンは、フロイトにとって理想郷だったのでしょう」と明かします。そしてロンドンの終の住処が博物館として公開されており、フロイトが好んで収集したハガキや書籍のコレクションが展示されているほか、書斎やライブラリが当時のまま残されています。
続いて、イギリスが生んだ看護学の開祖、フローレンス・ナイチンゲールの博物館へ。
「彼女は最近話題の在宅医療や在宅介護などの問題を、150年も前に発想して実践に移しているんですよね。先見性と洞察力、行動力は並大抵のものではない。驚くべきことは、看護学という概念すらなかった時代に、人間の暮らしと看護がどのように密接に結びついているかということを考察して、現代の抱えている思想を確立し、それを実践したことです。祖国イギリスでは看護師の模範となっています」

今でこそ、“白衣の天使”といって尊敬される職業ですが、当時、看護師は貧困階級の出身者がなるもので卑しい職業と考えられていました。それだけに、看護師の地位を確立し、さまざまな功績を残したナイチンゲールに、改めて尊敬の念を抱くと同時に、ひとりの女性としても強く魅了されました。
次にお話はイタリアのミュゼへ。イタリア・ボローニャにある「ボローニャ大学人体解剖博物館」のシンボル「解剖されたヴィーナス」像は、人体模型にもかかわらず今にも動き出しそうなほどリアルで妖艶な姿をしており、美術品としても素晴らしいものです。中世初の人体解剖が行われたボローニャ大学のこの博物館は、18世紀中頃のローマ教皇で、枢機卿時代から解剖に興味があったボローニャ生まれのベネディクト14世の強い思いがあり設立されたそうですが、ローマ教皇と解剖という不思議なつながりに関しても皆さん興味を覚えておられる様子でした。
ここにしかないミュゼを解説しながら、フランス人とその他の国の民族性の違いも説明してくださった宇田川氏。3回にわたってフランスをはじめ、ヨーロッパの珍しい美術館・博物館を宇田川氏のガイドでともに巡り、各地の歴史や文化、暮らしに関するさまざまなお話に触れられる講座となりました。
[FIN]