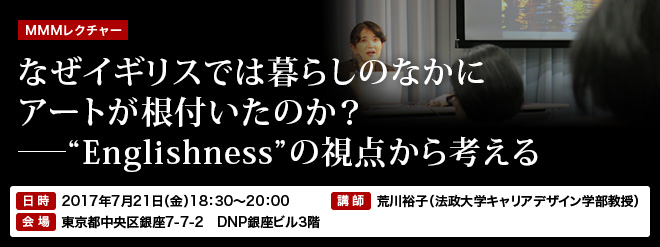MMMで7月まで開催されていた「ロンドンミュージアム特集」にちなんで、7月21日にイギリスのアートに関するレクチャーが行われました。講師にお招きしたのは、イギリスを中心とする西洋近代美術史がご専門の荒川裕子先生。イギリスらしさを意味する“Englishness”をキーワードに、暮らしとアートの関係やコミュニケーションとしてのアートのあり方をお話しいただきました。
「アートという観点からみますと、実はイギリスはフランスに憧れつつも、敵のようなイメージを持っていたと言えます。つまり、フランスには負けたくない気持ちを持ちながら、その中でなんとかイギリスらしさ、つまりEnglishnessをつくり出してきたというのがこの国のアートの歩み。Englishnessとは何か、今日私たちがイギリスに抱くイメージはどこにそのルーツがあるのか、現代のイギリス文化をつくり出した根っこの部分に焦点を当てて今日はお話をしていきたいと思います」
荒川先生のこのような言葉からイギリス美術のルーツを探る“旅”が始まりました。

まず、Englishnessのルーツである、18世紀後半に起こった産業革命の時代に遡っていきました。当時、イギリスはヴィクトリア女王(在位1837−1901)が統治。その間、国内で大きな戦争もなく、世界の工場としてモノをつくり出し、売ることでイギリスの繁栄の基盤が出来上がりました。そして、イギリス独自の美術が確立したのもこの頃のことで、イギリス美術を全土に広めるために美術館が建設されたと荒川先生は説明します。1824年にはナショナル・ギャラリーが、1856年にはナショナル・ポートレート・ギャラリーなどが開館し、この時代に次々とイギリスの主だった美術館が誕生しました。実はこうした美術館建設ラッシュには、1851年にロンドンで行われた第1回万国博覧会開催も背景にあったそうです。
「万博では、自国開催にもかかわらず、イギリス製品のデザインのレベルの低さを露呈してしまいました。そこで、工場でモノをつくる労働者たちに無料でアートを見せることで彼らの美意識を高め、イギリス製品のレベルを高めようとしたのです」

そして、時代が下ったヴィクトリア朝最盛期には、美術評論家であり思想家のジョン・ラスキンとその教えを受けたデザイナー兼詩人、ウィリアム・モリスの二人が登場し、イギリス美術の発展に貢献しました。「この大量生産の時期は、労働者たちは工場の歯車のひとつであるという働き方が始まった時代です。彼らの生活こそ、美しくしていかなければならない、そのためには労働者たちが手づくりでモノをつくり、美の喜びを感じてもらいたいと考えたのです。本当に美しいものは、飾ったり眺めたりするのではなく、アーツとクラフツ(美術と工芸品)の境目を設けず、美を意識するような暮らしをすることが重要だということ。それを理論的に訴えたのがラスキンで、モリスがデザイナーとして実践したのです」と荒川先生はおっしゃいます。
さらに、イギリス美術というと私たちは風景画をイメージしますが、このことについても言及し、「“ライバル国”フランスのような美術表現とは異なるものを生み出したいという思いがあったから」と荒川先生。フランスへのライバル心もまた、イギリス人の風景に対する豊かな感性につながっていたことに、参加者の皆さんも驚かれている様子がうかがえました。
大正時代には民藝運動という形で日本の柳宗悦らにも影響を与えた“Englishness”。日本人の感性にも近いイギリス美術に、親近感をもつことができた一夜となりました。
[FIN]