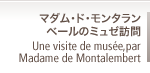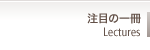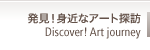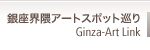![]()
![]()
メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド(MMM)のある銀座界隈には企業が運営する美術館やギャラリーなどが、数多く点在しています。銀座のMMMにお越しの際、併せて訪問いただきたい、こうしたアートスポットを中心にご紹介してまいります。
今回は、緑豊かな日比谷公園の一角に建つ、千代田区立日比谷図書文化館で開催されている「藤田嗣治 本のしごと〜日本での装幀を中心に」(2013年6月3日まで)を訪れました。パリで活躍したエコール・ド・パリの画家、藤田嗣治(ふじた・つぐはる)が主に日本で手がけた「本のしごと」を中心に紹介しています。
 ■所在地
■所在地- 東京都千代田区日比谷公園1-4
- ■Tel
- 03-3502-3340(代)
- ■開設年
- 1908年に日比谷図書館として設立。1943年に都立図書館となり、
2008年、千代田区へ移管。
2011年に千代田区立日比谷図書文化館として再オープン。 - ■運営コンセプト
- 常設展示室では、文化財とデジタル技術を駆使して千代田区の歴史と文化および町の魅力を紹介。特別展示室では、千代田エリアの文化をさまざまな角度から紹介する特別展示を実施。
- ■URL
- https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya/
- ■開催中の展覧会
- 「日比谷図書文化館特別展 藤田嗣治 本のしごと〜日本での装幀を中心に」/2013年4月4日(木)〜6月3日(月)
- ■入場料
- 〈常設展〉無料
〈特別展〉一般:300円/大学・高校生:200円
※千代田区民・中学生以下、障害者手帳をお持ちの方および付添の方1名は無料 - ■休館日
- 毎月第3月曜日
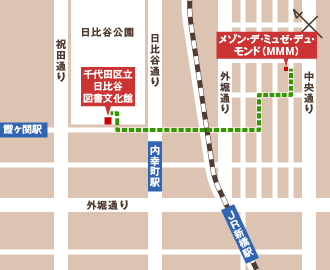
- ■開館時間
- 10:00-20:00(土曜日19:00まで、日曜日・祝日17:00まで、入室は閉室の30分前まで)
- ■アクセス
- 都営三田線内幸町駅より徒歩3分。東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線霞ヶ関駅より徒歩5分。JR新橋駅より徒歩12分。
- ■運営企業
- 日比谷ルネッサンスグループ
2011年11月に改装を経て再オープンした千代田区立日比谷図書文化館は、「図書館」機能のほか、さまざまな展示を行う「ミュージアム」、イベントを行う「カレッジ」などを持つ複合施設です。銀座界隈アートスポット巡りでは「名取洋之助 日本工房と名取学校」以来2度目の訪問となりました。
1階の入り口近くにある「特別展示室」で6月3日まで開催されているのが、藤田嗣治(1886-1968)の展覧会です。藤田といえば、独自の画法を駆使した裸婦像で注目され、「乳白色の肌」とフランス画壇から絶賛されたエコール・ド・パリを代表する画家です。藤田の渡仏100周年を記念して開催された今回の展覧会では、“画家”藤田嗣治ではなく、“装幀家”としての作品が紹介されています。
挿絵本は、古くからヨーロッパでは一流の画家たちが手がける「芸術作品」でした。
とくに、藤田がパリに渡った20世紀初頭は、シャガールやピカソといった画家たちも挿絵用のオリジナル版画を制作するなど、挿絵本全盛の時代でした。そして、藤田もまた挿絵本の世界に魅了されていきました。
展覧会を監修した京都造形芸術大学准教授の林洋子(はやし・ようこ)先生は、第一線で藤田作品を研究されています。
「藤田が日本で手がけた本のしごとが一堂に会するのは初めてのことです。電子書籍が流通している中、戦前の人がいかに本を大事にしてきたかを知るいい機会になると思います」と見どころを語ってくださいました。
展示室には、菊池寛や横光利一、林芙美子ら日本の文学者の著作を中心に、ジャン・コクトーやポール・クローデルといったフランス人芸術家たちの著作の表紙・挿絵なども含め約100点が出品されていました。
中でも“目玉”のひとつは、入って左手の壁側に展示されている『ホーム・ライフ』や『婦人之友』などの婦人雑誌です。「パリ帰りの藤田に求められたのは、フランスのエスプリのようなものを描いてほしいということでした。今はインターネットなどで容易に情報が入手できますが、当時のフランスは船で片道40日かかるうえ、往復の運賃が家一軒分といわれるほど遠い国でした。つまり藤田は日本の人々にとって“フランスの窓”となったのです」。華やかな衣装を身にまとった外国人女性や、四季折々のフランスの名所などが描かれた装幀に心を奪われたと同時に、戦前にこうした贅沢な雑誌が作られていたことに驚きました。
「たとえば、婦人雑誌であれば華やかさを演出したり、詩集であれば線描だけでシンプルにしたりとか、フランス語でも、日本語でも遊び心があると同時に書き手に寄り添った装幀をする人でした。絵のスタイルはありますが、ワンパターンではない。そこは稼ぐためにやっているわけではなく、書き手のために作ってあげたいという気持ちからなんでしょうね」
 ▲フランス時代の作品が展示されるコーナー。この時
▲フランス時代の作品が展示されるコーナー。この時
期の挿絵本には、「記憶の中の日本」を描いたという
また、今回の展覧会のもうひとつのテーマとして、「千代田区にゆかりのある作家の展覧会にしたい」という思いがあったとか。藤田は、当時の麹町区(現:千代田区六番町)に家とアトリエを構えていた時期があり、その様子を写した写真も公開されていました。写真は、日本を代表する写真家、土門拳が撮影し、大きな暖炉やヨーロッパの置物などがある室内の様子や、猫を膝に乗せて読書をしてくつろぐ姿など、日常の藤田を垣間見ることができました。
フランス画壇で活躍し、日本とフランスの二つの祖国を愛した藤田嗣治。
油彩画だけではない幅広い才能を持った藤田の世界観を体感することができる展覧会へぜひ足をお運びください。
 今展覧会は、きっと今までに見たことがない藤田に出会える場所だと思います。美術ファンの方も図書館ファンの方も、展示されている作品の細部をご覧になれば、藤田を起点に文化人たちの幅広いネットワークが見えてくるでしょう。藤田の渡仏100周年の今年は、色々な美術館で藤田展が開催されますので、こちらの展覧会を皮切りにさまざまな“藤田ワールド”をお楽しみいただければと思います。
京都造形芸術大学 林 洋子准教授
今展覧会は、きっと今までに見たことがない藤田に出会える場所だと思います。美術ファンの方も図書館ファンの方も、展示されている作品の細部をご覧になれば、藤田を起点に文化人たちの幅広いネットワークが見えてくるでしょう。藤田の渡仏100周年の今年は、色々な美術館で藤田展が開催されますので、こちらの展覧会を皮切りにさまざまな“藤田ワールド”をお楽しみいただければと思います。
京都造形芸術大学 林 洋子准教授