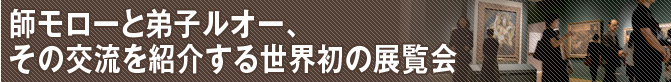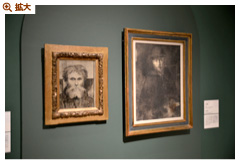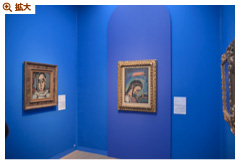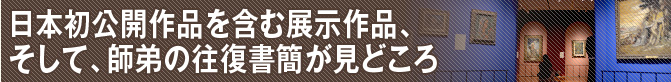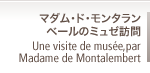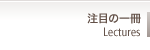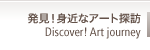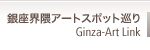![]()
![]()
メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド(MMM)のある銀座界隈には企業が運営する美術館やギャラリーなどが、数多く点在しています。銀座のMMMにお越しの際、併せて訪問いただきたい、こうしたアートスポットを中心にご紹介してまいります。
2003年の開館以来、「都会のオアシス」として親しまれている東京・汐留の「パナソニック 汐留ミュージアム」。今回は、その開館10周年を記念して特別展を開催中の汐留ミュージアムを再度訪問しました。展覧会の名は「モローとルオー 聖なるものの継承と変容」(2013年12月10日まで)。2015年パリでの開催に先駆けて幕開けした、注目の展覧会です。
 ■所在地
■所在地- 東京都港区東新橋1-5-1
パナソニック東京汐留
ビル4F - ■Tel
- 03-5777-8600
(ハローダイヤル) - ■URL
- http://panasonic.co.jp/es/museum/
- ■観覧料
- 展覧会により異なります。
障がい者手帳をご提示の方、および付添者1名まで無料でご入館いただけます。
20名以上は各100円引きとなります。(60歳以上は除く) - ■アクセス
- JR新橋駅「銀座口」より徒歩8分、東京メトロ銀座線新橋駅2番出口より 徒歩6分、都営浅草線新橋駅改札より徒歩6分、都営大江戸線汐留駅「3・4番出口」より徒歩5分 パナソニック東京汐留ビル内4階
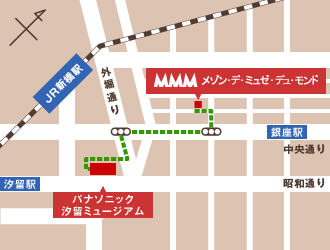
- ■休館日
- 水曜日(祝・祭日は開館)、展示替え期間、年末年始
- ■開館時間
- 10:00-18:00(ご入館は17:30まで)
*各データは2013年9月現在のものです。
世紀末象徴主義の巨匠ギュスターヴ・モロー(1826-1898)は、1892年からパリの国立美術学校(エコール・デ・ボザール)で教鞭を執りました。自らの作風を押し付けることなく、自由な教育方針を貫くモローの教室からは、マティスやマルケなど多くの才能ある若手画家が輩出しましたが、中でも、いちばんの愛弟子がジョルジュ・ルオー(1871-1958)でした。モローはルオーの才能を見出し、指導するのみならず、自らの死に際して5,000フランを遺すなど、物心両面で弟子を支えました。そしてルオーは、モローの死後に開館したモロー美術館の初代館長に就任することで、自らの絵画制作に没頭する環境を手にし、やがて「20世紀最大の宗教画家」と称される存在となったのでした。
今回の展覧会を企画した「パナソニック 汐留ミュージアム(Shiodome Museum Rouault Gallery)」は、「ルオー」の名を冠する世界で唯一の美術館です。館内には常設展示スペース「ルオー・ギャラリー」があり、約230点のルオー・コレクションから、そのときどきのテーマに応じた作品を公開しています。開館10周年記念として開催されている本展は、モローとルオーという、フランスの19世紀と20世紀を代表するふたりの画家の師弟関係に焦点を絞った、世界で初めての展覧会として注目を集めています。
「1点たりとも変更のきかない渾身の作品セレクション」
本展の監修を務めたギュスターヴ・モロー美術館館長のマリー=セシル・フォレスト氏は、こう語ります。フランスからの出品作56点のうち、半数以上が日本初公開という豪華なラインナップで、モローとルオーの芸術の軌跡と心の交流を探ります。たとえば、国立美術学校時代のルオーに焦点を当てた第一セクションでは、ローマ賞をはじめ、数々の賞に挑んだ若きルオーと、丁寧に指導するモローの師弟関係が、油彩や習作をはじめとするさまざまな作品を通じて浮かび上がってきます。また、モロー晩年の抽象画的作品と、深い精神性をたたえたルオーの作品が混在する展示は、モローがいかに近代的な画家であったか、そして、その後継者であるルオーが、師の芸術を独自の芸術へと変容させていった過程を雄弁に物語る内容となっています。
 ▲モローの大作《ユピテルとセメレ》(左)と、ローマ賞の最終試験のために描かれたルオーの《死せるキリストとその死を悼む聖女たち》
▲モローの大作《ユピテルとセメレ》(左)と、ローマ賞の最終試験のために描かれたルオーの《死せるキリストとその死を悼む聖女たち》
そして今回の展覧会には、絵画のほかに、もうひとつの見どころがあります。それが、モローとルオーの往復書簡です。会場の一画に設けられたコーナーでは、「親愛なる我が子」「最高の指導者、大いなる父」と呼び合った師弟が、ときに絵画への情熱を込め、ときにユーモアを交えて綴った複数の手紙が日本語で紹介されており、ふたりの心の交流に触れることができます。
世紀末パリを舞台に“美しき師弟愛”の物語を紡いだモローとルオー。その芸術と心の交流を追うこの展覧会は、2015年にパリのモロー美術館へと巡回予定です。世界に先駆けて開幕した本展へ、ぜひ、足をお運びください。
フランス象徴主義の巨匠ギュスターヴ・モローと、20世紀最大の宗教画家と呼ばれるジョルジュ・ルオー。日本でも人気の高いこのふたりの画家の師弟を超えた絆、そして芸術上の結びつきに焦点を当てた世界で初めての画期的な展覧会です。モロー美術館、ポンピドー・センターなどフランスの主要美術館、そして個人所蔵家から出品される作品の半数以上が日本初公開!モローファンもルオーファンも必見の展覧会です。 パナソニック 汐留ミュージアム 学芸員 萩原敦子