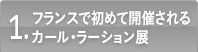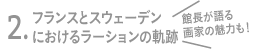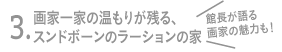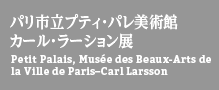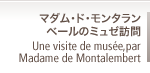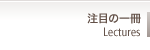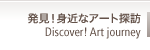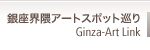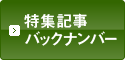今月と来月は、パリ市立プティ・パレ美術館の企画展をご紹介します。第一弾は、現在開催中のスウェーデンの国民的なアーティスト、カール・ラーション(Carl Larsson/1853-1919)の回顧展です。カール・ラーションは19世紀末から20世紀初頭にかけてスウェーデン、またフランスを拠点に活躍した画家。とりわけ自身の家族を描いた水彩画のシリーズ作品で知られています。何気ない日常のひとコマを切り取ったラーションの絵画は穏やかで温かな雰囲気に満ちていて、見る者を幸せな気持ちにさせてくれます。
カール・ラーションはフランスとはたいへんゆかりの深い画家ですが、フランスで回顧展が開催されるのは本展が初。今回、ストックホルムの国立美術館と、かつてラーションが暮らしたスウェーデン中部の町、スンドボーン(Sundborn)の「カール・ラーション記念館」の協力によって水彩画、油彩画、版画、家具など、約120点が集められました。
ラーションは1853年にストックホルムの貧しい家庭に生まれました。ストックホルムの王立美術学校で学んだのち、パリへとやってきたのは1877年のこと。芸術の都パリにてその力量を試すべく、サロンへの出品を積極的に行いながら10年以上にわたりフランスとスウェーデンを行き来する生活を送りました。1882年にパリ近郊のフォンテーヌブローの森に程近い小さな村、グレ=シュル=ロワン(Grez-sur-Loing)へと移住し、アングロ・サクソンやスカンジナヴィア系の芸術家グループの中心的存在として画業に励みます。生涯の伴侶となるカーリンと婚約したのも、このグレ=シュル=ロワンにおいてのことでした。
パリ万博で1等のメダルを獲った1889年、ラーションはフランスを離れ、拠点をスウェーデンに移すことを決意します。そして母国で初個展を開催したり、国立美術館の階段の壁画を手掛けたりと制作に励む日々を送り、画家としての評価を確立していきました。しかし、全てが順風満帆というわけではありませんでした。国立美術館のホールの装飾のために描いた《冬至の犠牲》が、モチーフに関わる論争の末、展示を拒否されるなど、失意の出来事も起こります。最終的にこの作品が国立美術館に展示されるのは、ラーションの死から半世紀以上経ってからのことでした。
こうした大作へ取り組む傍ら、ラーションがとりわけ精力的に描いたのが、自身の家族の日常でした。ストックホルムから230キロ離れたスンドボーンの村は、ラーションが妻や子どもたちと暮らした安らぎの地。ラーションは家族のいる日常の情景を、豊かな色彩と細やかなタッチで水彩画の中に収め、そのシリーズをまとめた画集『わたしの家』は大きな評判を呼びます。その後、ラーションの画集は次々に出版され、その人気はスウェーデンに留まらず、国際的なものとなっていったのです。
次ページでは、フランスとスウェーデンにおける
ラーションの軌跡をご紹介します。>>
Update:2014.5.1 文・写真:増田葉子(Yoko Masuda)![]()
- ■会期
- 2014年3月7日(金)〜7月7日(月)
- ■会場
- パリ市立プティ・パレ美術館
- ■所在地
- Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
- ■Tel
- +33 (0) 1 53 43 40 00
- ■URL
- http://www.petitpalais.paris.fr/
- ■開館時間
- 10:00-18:00
*木曜日は20:00まで開館 - ■休館日
- 月曜日、祝日
- ■入場料
- 一般:8ユーロ
割引:6ユーロ
14歳〜26歳:4ユーロ
13歳以下:無料 - ■アクセス
- 地下鉄1番線または13番線Champs-Élysées Clémenceau駅下車、徒歩約2分。
RER C線Invalides駅下車、徒歩約5分 - ※この情報は2014年5月更新時のものです。
- ■MMMライブラリでは、カール・ラーション展のカタログや、パリ市立プティ・パレ美術館の関連書籍などを閲覧いただけます。
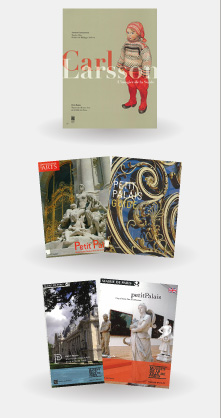
*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。