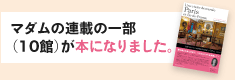扇子は、かつては貴族の持ちもので、《井戸端のリベカ》(1770-1775年)のように、よく知られた絵画から題材をとった神話や聖書の物語が描かれていました。ルイ15世(1710-1774)の時代になると、牧歌的な主題や男女の恋の一場面が描かれるようになります。《逢瀬》(1720年頃)は、ターコイズブルーの絹地に若い男と恋人を描いた一品で、中心となる主題を取り囲む余白には、当時流行していた中国風の装飾が施され、東洋風の装いの人々があしらわれています。その後、革命期になると扇子はいったん姿を消しますが、総裁政府時代(1795年から1799年までの4年間をさす。ナポレオンのクーデターにより終末を迎えた)を迎えて、軽やかなドレスが流行すると、それに伴い小ぶりな扇子が作られるようになります。
《思い出》(1830年)と題された、骨、金属、絹でできた見事な扇子は、当時、扇子が重要なファッションアイテムとして再登場したことを物語る品。そして第二帝政期には、扇子は再び黄金時代を迎えます。1836年にクロモリトグラフィーの手法が開発され、同一デザインの大量生産が可能になると、扇子は大流行し、フランスは西洋で唯一の扇子の生産国となったのです。19世紀末には、マネ(1832-1883)やルノワール(1841-1919)、ピサロ(1830-1903)、ゴーギャン(1848-1903)といった多くの有名な画家たちが、扇面に絵を描いたり、優雅に扇子を持つ女性を絵画に登場させたりしています。
20世紀初頭、ベル・エポックの時代には《薔薇色の楽園》(1900年)のような羽扇子が流行し、アール・ヌーヴォーとともに新しい主題が登場します。《新世紀の訪れ》(1900年)のような若い女性をモチーフにしたものや、《薔薇色の楽園》や《薔薇の涙》(1905年)のように花を主題にしたものなどです。《薔薇色の楽園》は日本の影響がうかがえ、《薔薇の涙》は骨は白い真珠層、扇面は絹地にグアッシュで描かれた作品です。
ふたつの大戦の間、ファッションアイテムとしての扇は廃れましたが、大量生産されて広告媒体として用いられるようになります。とりわけ、大正末期から昭和初期の日本では、広告媒体として団扇がさかんに用いられたといいます。
第二次大戦後は、クリスチャン・ディオール(1905-1957)のショーで使われたのをきっかけに、カール・ラガーフェルド(1933-)が手掛けたシャネルのコレクションをはじめとして、扇子はオートクチュールのコレクションの一部となっています。このことが扇子再生の原動力となり、高級扇子を専門とする最後のアトリエであるアンヌ・オグエのアトリエは今なお活動を続け、オートクチュールの扇子を作りながら、その技を後世に伝えているのです。
今年、美術館の創立20周年および建物の内装装飾の120周年という節目の年を迎えたこのミュゼでは現在、エルヴェ・オグエのコレクションの名品選(2014年3月12日まで)が開催されています。ぜひ、お訪ねになってみてください。
友情を込めて。