 |
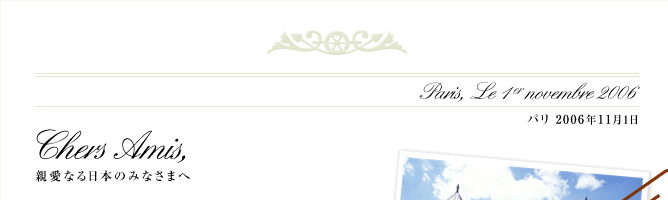 |
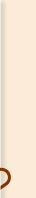 |
 |
 |
 |
 |
▲装飾芸術美術館のあるブファール通り。
©A.de Montalembert |
|
 |
18世紀、ワインの取引で富を築いたボルドーは、フランス随一の港町として繁栄を謳歌しました。多くの貴族や上流階級の市民たちが財を成しましたが、当時の町議会議員のピエール・レイモン・ラランドもそのひとり。さとうきびやコーヒーのプランテーションで富を蓄えた彼はその財力を注ぎ、のちに装飾美術館となる優美な屋敷を建てさせたのです。
ボルドーの建築家エティエンヌ・ラクロット(1728-1812)の設計に基づき、1779年に完成したラランドの私邸は、18世紀フランスらしい古典主義建築の特徴が随所に見られる邸宅です。簡素な美を湛えた白亜の館は「entre cour et jardin(中庭と外庭の間)」と呼ばれる場所に建ち、その手前には、豪華な幌付きの四輪馬車でもたやすく操作できるようにという配慮から、半円形の石畳の中庭が広がります。左手に見えるのは、かつて馬車用の厩舎や車庫として用いられていた建物ですが、今日ではミュゼの一部となっています。この邸宅は、18世紀の建築当初の姿のままの調和のとれた美しさで訪問者を迎え入れるのです。
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
革命の時代を迎えると、この邸宅は押収され、19世紀にはさまざまな人の手から手へと渡ることとなりました。そして1880年、ボルドー市によって買い取られ、警察署として使われたのち、1925年に美術館、1984年にボルドー装飾芸術美術館に生まれ変わったのです。
それでは、18世紀から19世紀にかけて、この町の富裕層が辿った歴史やその暮らしぶりに想いを馳せつつ、このミュゼのコレクションを巡ってみることにいたしましょう。
1階には、建築当初のままのボワズリー(板張りの壁)や、コナラとマホガニーの寄木張りの床、ルイ15世およびルイ16世時代の暖炉などが残されています。玄関ホールから階上へと伸びる壮麗な石階段の美しい手すりは、まさに18世紀ボルドーの鉄細工の傑作といえましょう。 |
 |
 |
▲半円形をした石畳の中庭。
©A.de Montalembert |
|
  |
 |
また、玄関ホールの控えの間では、港町ボルドーの繁栄とその歴史を今に伝えるパノラマ画や彫刻作品が飾られていますが、そのなかには次のような作品があります。
| ・ |
モンテスキュー(1689-1755)の大理石胸像
啓蒙思想家モンテスキューは、ボルドーのブレド城に暮らしました。その著作は、司法・行政・立法の三権分立に基づく自由主義憲法の理論の起源として知られています。 |
| ・ |
フランス国王ルイ15世(1710-74)のブロンズ像 ジャン=バプティスト・ルモワン作
ボルドーのロワイヤル広場に置かれていた大きな彫像のミニチュア。オリジナルは1792年に撤去されたのち、大砲に加工されてしまいました。 |
そして、18世紀の邸宅らしく、控えの間の奥には外庭に臨む応接間が続きます。 |
 |
| |
|
|
 |
 |
 |
▲18世紀の食卓が再現された1階の食堂。
Musée des Arts décoratifs, Bordeaux
© DEC, Photo L.Gauthier |
|
 |
中庭に面した食堂では、金銀細工品やファイアンス陶器といったボルドーの工芸品コレクションが展示されています。ボルドーの陶器は、製作された期間は短いながらも(1787年から1790年まで)繊細かつ丈夫で、その品質は極上。縁取り模様を施した田舎風の愛らしい花束といったモチーフが好まれたようです。このファイアンス陶器の食器セットを用いて見事に再現された18世紀の食卓は、この食堂の見どころのひとつです。また、港町ボルドーを代表的する調度品のひとつに、ブラジルやキューバといった外国産のマホガニーを用いた戸棚がありますが、この食堂に置かれたルイ15世時代の戸棚はとても素晴らしい一品です。扉が開けられた上部3分の2は陶磁器などの飾り棚として用いられ、扉の閉ざされた下部3分の1は収納家具としての役割を果たしています。 |
 |
| |
|
|
|
|
 |
食堂に続くのは、寄贈者の名にちなみ「クルーズ・ゲスティエの間」と呼ばれる応接間。20世紀初頭のゲスティエ邸の一室をそのままに復元したこの部屋で、調度品や中国陶磁器(壷や花瓶などの大型陶磁器)をご覧になれば、ひとりのボルドー商人の18世紀志向を手に取るように感じていただけることと思います。たとえば、アントワーヌ=ルイ・バリー(1795-1875)によるブロンズの動物像は、彼が騎馬猟に熱中していたことを物語る品です。 |
 |
| |
|
|
 |
2階は、ボルドーのさまざまな邸宅から集められたボワズリーを用いて改修されました。いくつもあるサロンのひとつひとつが異なる様式でありながらも、美しい調和が見られるのはそのためでしょうね。ここでご覧になれるのは、18世紀フランスのファイアンス陶器(ルーアン、マルセイユ、ヌヴェール、ムスティエ)や、デルフト焼き(青単色の17世紀オランダ陶器)の名品の数々──。そして、ガラス工芸品の見事なコレクションが展示されているのが「黄水仙の間」です。この部屋は、ルイ16世時代のパリで作られ、優れた品質を保証する焼印の押されたボワズリーと、それに調和するように置かれた家具調度が素晴らしい一室で、かつては応接間として用いられていましたが、今は寝室に改築されています。1775年にパリで「maître(職人)」の称号を受けたL.M. プリュヴィネの焼印が押された「ポーランド風の」ベッドの上には、黄色と青の絹で織られたカバーが掛けられています。 |
 |
 |
▲寝室に改装された「黄水仙の間」。
Musée des Arts décoratifs, Bordeaux
© DEC, Photo L.Gauthier |
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
▲緑色のボワズリーが美しい2階のサロン。
Musée des Arts décoratifs, Bordeaux
© DEC, Photo L.Gauthier |
|
 |
お次は、緑色のボワズリーが美しいサロンへお入りください。扉に施された金色の装飾が人目を引くロココ様式のボワズリー(1736年)が素晴らしく、室内にはこのボワズリーと同じく摂政時代に作られたマホガニー製の優美な「スクリバン机」が置かれています。ボルドーの邸宅でよく見られる「スクリバン机」とは、箪笥とスクレテール(書き物机)、書棚を組み合わせた、港町ボルドーならではの実用的な家具のひとつです。
そして、ソファーの上にある1746年製の掛け時計にも目を留めてくださいね。真鍮の切りばめ細工が素晴らしい一品で、女性を象ったブロンズの装飾が施されています。また、ロココ風に彩色された古楽器スピネット(小型のチェンバロ)の美しさにも心惹かれました。華やかなフリジア帽やトリコロールのリボンを、楽器の外側はもちろん内側にまで描き込んだこの古楽器は、革命期ならではの美を宿す一品といえましょう。 |
  |
| |
|
|
|
|
 |
さて、地上階にある他の建物をまわってみることにいたしましょう。4つの小さな応接間は改修が行われ、レイモン・ジャンヴロという人物による19世紀のコレクションが展示されています。彼は、フランス最後の国王たち(ルイ16世、ルイ18世、シャルル10世)とその最後の後継者、シャンボール伯爵にまつわるものすべてに情熱を注いだボルドーのコレクターです。
このミュゼを訪れれば誰しも、18世紀ボルドーの典型的な貴族の邸宅に招かれたかのような錯覚を覚えるのではないでしょうか。それは、なんと洗練された安寧な暮らしだったのでしょう。しかし、ここでわたくしたちが触れるのは、それだけではありません。17世紀から20世紀にいたるまでのボルドー、そしてフランス、ヨーロッパ中の装飾美術の流れを辿ることができるのです。
今秋、現代作品に関する美術館オープンの一環として、今年60歳を迎えたボルドー生まれの建築デザイナー、シルヴァン・デュビュイソンの興味深い特別展が開催されます。デュビュイソンは80年代を代表するもっともユニークなクリエーターのひとりで、幅広いジャンルで活躍しています。たとえば、アルミ製のベッドに空想の海へと誘う帆の形をしたパラシュート生地を付けた作品「無意識」のように、ひとつひとつに魂を吹き込んだ芸術作品を発表することもあれば、パンテオンやパリ、ノートルダム大聖堂などの公共施設の改修を行うこともあり、最近ではパリの装飾美術館の改装を手がけました。その一方で、カルティエや、ドゥコー、エルメスといった企業のためにもその才能を惜しみなく発揮しますし、文化省からの注文も受けているのです。1991年にはジャック・ラング大臣の書斎に置く家具の制作も行いました。このアーティストが追い続けるものを、概念的、そして技法的な点から紐解いていくこの特別展は、きっとみなさまにも興味深いものになることと思います。
さて、ミュゼご訪問の締めくくりには、是非、雰囲気の良いカフェ・レストランでのひとときをお楽しみくださいね。中庭のテーブルから眺める石造りのファサードの美しさは格別ですのよ。
親愛をこめて
|
 |
| |
|
|
 |
 |
▲装飾芸術美術館の石畳の中庭。
©A.de Montalembert |
|
 |
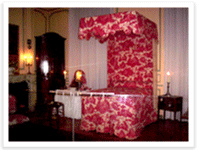 |
▲趣のある寝室。
©A.de Montalembert |
|
 |
 |
▲館内で見られる陶器コレクション。
©A.de Montalembert |
|
 |
|
 |
|