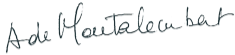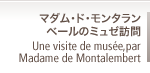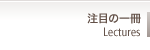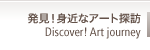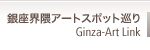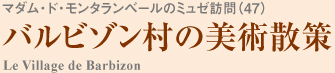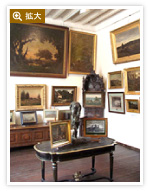テオドール・ルソーの親友であり、バルビゾン派のリーダー的存在であったジャン=フランソワ・ミレーもまた、1853年にパリを離れ、妻と子どもたちを連れてバルビゾンに移り住みます。あまり裕福ではなかったミレーは質素な一軒家を手に入れ、その離れの開口部を広げてアトリエとしました。その地で《晩鐘》(1853年)や《落ち穂拾い》(1857年)といった農民たちの姿を描いた作品を制作し、田舎の暮らしを繊細な目で観察しながら、写実主義を代表する画家となっていったのです。ミレーはアトリエの中で、記憶をたよりに絵を描く手法を取っていました。完璧主義の彼は、リウマチに悩まされながらも、この湿っぽいアトリエで制作することをやめませんでした。そして、9人の子どもたちを養いながら、死ぬまで慎ましく、厳格な生活を送ったのです。
現在、ジャン=フランソワ・ミレー記念館となっている、ミレーの家の外観は今日も変わっていませんが、屋内は改装され、画家の絵が所々に残されているのみです。しかしながら、《晩鐘》と《落ち穂拾い》のエッチングが展示されているアトリエは、昔の姿のまま、その魅力を私たちに伝えてくれます。
入口の両脇に当時の芸術家たちの写真が飾られており、非常に興味深く拝見いたしました。食堂にはミレーのデッサンや版画がたくさん展示されています。ミレー家の人々が集う場であった台所では、風景画をテーマに現代の画家の展覧会が催されていました。
バルビゾン派が終焉を迎えるのは、 偉大な画家たちが死を迎えた1875年頃のことでした。彼らは、自然を研究し、時間帯や天気、季節によって移り変わる光の表現を追求することで風景画に革命を起こし、その流れは印象派の画家たちに受け継がれていくことになります。
現在でもバルビゾンには田舎ならではの美点が残されています。フォンテーヌブローの森は、画家たちが絵を制作した当時の面影を強く残しながら、多くの観光客が訪れる場所になりました。1861年に芸術保護地区(後に生態保護地区となる)に制定され、世界で初めて自然保護に関する措置が取られたのは、実は、森を大切にしたバルビゾン派の芸術家たちのおかげだったことを付け加えて、この手紙の結びとします。
友情を込めて。