 |
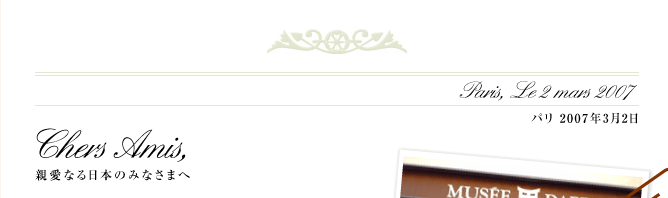 |
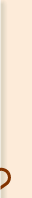 |
 |
 |
パリのケ・ブランリ美術館のオープンが大きな熱狂とともに人々に迎えられて以来、フランスでは「原初美術(Arts Premiers)」が流行し、レンヌやロシュフォール、ルーアン、トゥールーズなど多くの地方美術館でもこのテーマの展覧会が催されるようになりました。
原初美術といえば、すでに20世紀初頭には、ブラックやヴラマンク、ドランといった一部の芸術家たちがアフリカの美術品を収集していました。そして、彼らのアトリエを訪れたピカソやマティスをはじめとする多くの芸術家たちがアフリカ美術に魅せられ、大きな影響を受けたのでした。 |
 |
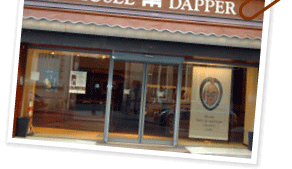 |
▲ダッペール美術館の外観
©A. de Montalembert |
 |
|
| |
|
|
|
 |
 |
▲ ダッペール美術館の外観
©A.de Montalembert |
 |
|
 |
1986年、人々にアフリカ美術の素晴らしさを広めることになる一軒の魅力的な美術館がパリにオープンました。それが、ダッペール美術館です。今回は、アフリカ美術の愛好家であれば誰もが訪れるこのミュゼへと皆さまをご案内いたしましょう。
この美術館が建つのはパリ16区の静かな通り。広い通り沿いに私邸や高級アパルトマンが建ち、上品な雰囲気に溢れたフォッシュ通りと、この地区の“シック”な客層に見合った店が軒を並べるヴィクトル・ユゴー通りの間に位置しています。
訪れる人々を温かく迎え入れるこのミュゼの建物は、もともとは1910年に建てられた小さな私邸。2000年には無駄な装飾のないシンプルなスタイルに改装され、展示品が見事に際立つことになりました。 |
  |
| |
|
|
|
|
 |
この美術館では、アフリカ美術だけでなく、アフリカ大陸から離散したあらゆる民族の文化が紹介されています。たとえば、アフリカ出身の奴隷にルーツをもつ北アメリカの黒人たち。彼らが生み出した文体や絵、彫刻、芝居などには、アフリカから遠く離れた地で大きな共同体を作り上げた彼らならではのアイデンティティと文化が息づいています。このように、ダッペール美術館では、世界中に散り散りになってしまった、それぞれの民族文化への理解を深めることにも力を注いでいるのです。
このミュゼでは今、ガボンの彫刻を紹介する特別展が催されています。そのタイトルは『ガボン、精霊たちの存在』。なんと、想像力をかき立てられる題名なのでしょう。 |
 |
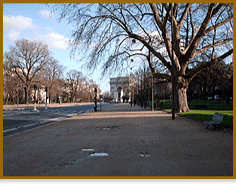 |
▲ フォッシュ通り
©A.de Montalembert |
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
ガボンはアフリカ、赤道直下に位置する国。大西洋に面し、国内のほぼ全域に長さ1200kmの大河「オグーエ河」が流れていることから、この国に暮らす人々は「オグーエ流域の民」と呼ばれているそうです。人口はおよそ100万人で、ファン族、ミイェーネ族、北のコタ族、プヌ族、南のヴィリ族など、異なるルートを経てアフリカの地にやってきた約40の民族が存在します。彼らは、フランス植民地時代を経験しながらも、それぞれの信仰や伝統的な習慣、そして昔ながらの社会生活や政治体系を今に受け継いできた民なのです。
国土の4分の3を深い森に覆われたこの国は、黒檀、マホガニー、オクメなどの森林資源の宝庫。ガボンで、とくに彫刻という芸術が花開いたのはそのためなのでしょうね。 |
 |
| |
|
|
 |
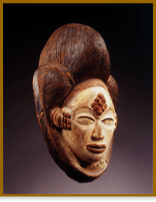 |
▲プヌ族、仮面《ミュキュイ》
©Archives Musée Dapper - photo Hughes Dubois. |
|
 |
この企画展で紹介されている130の品々は、ガボンの地で育まれた主な芸術の様式を網羅しています。つまり、ガボンの人々が古の時代から受け継いできた知恵と、その表現のあり方を知ることができるのです。
展示室に入ると、そこには仮面と聖遺物箱の彫像だけが照明の光に浮かび上がっていました。なんという存在感なのでしょう。そして館内は、宗教儀式に用いられたというこれらの彫刻を鑑賞するにふさわしい厳かな静けさに満ちていました。
仮面は葬儀や祭礼などの折に使われていたもので、部族によって様式が異なります。とりわけ目を惹くのは、カオリンと呼ばれる粘土で彩色された白い仮面。プヌ族の仮面は一風変わった髪形をしており、厚い唇をもったその顔は表現主義の作品を思わせます。(ガボン・プヌ族/ミュキュイ仮面)。そして、その表情の柔和なこと。モデルとなった女性もきっと、優しい面立ちをしていたのでしょうね。それに対して、ヴヴィ族とファン族(ガボン・ファン族/ンジル仮面)の仮面はより図案化され、飾り気のない形をしています。この白い粘土は今もなお、「ブウィティ」をはじめとする宗教儀式で、男女共に用いられているそうです。
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
そして、もっともよく知られたガボンの彫刻芸術といえば、彼らの祖先崇拝と繋がりをもつ聖遺物箱の彫刻でしょう。ガボンの人々にとって、死とは家族や同じ氏族の人々を分かつものではありません。生者と死者は、“聖遺物箱”というひとつの本質的な事物によって結びついているのです。樹皮やかご細工、皮革で作られたこの箱は、首領や戦士をはじめとする重要な地位にある人物の頭蓋骨と骸骨を収めるためのものでした。彼らがこの世を去ると、その遺骨は洗われ、パドゥークの木から採った赤い粉を塗られ、この箱に収められたのです。そして、彫像の顔はこの聖なる箱を護る役割を果たしていたそうです。 |
 |
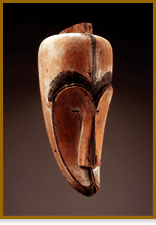 |
▲ ファン族、仮面《ンジル》
©Archives Musée Dapper - photo Hughes Dubois |
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
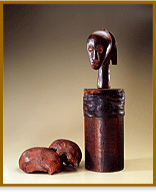 |
▲ ファン族、聖遺物箱付属の頭部の彫像《ウロ・ビエリ》
Musée Dapper, Paris
© Archives Musée Dapper
photo Gérald Berjonneau. |
 |
|
 |
これらの守護像の様式は、部族によって異なります。ファン族の像は木製で、リアリティ溢れる表現で彫られています(ガボン・ファン族/聖遺物箱付属の頭部の彫像ンロ・ビエリ)。コタ族の場合は、幾何学的な形をした木製の像で、銅と真鍮で覆われているために、黄金がかった美しい褐色をしています(ガボン・コタ族/聖遺物箱の像マホングウェ)。こうした彫像は聖遺物箱の付属品としての役割とは別に、さまざまな儀式においても大切な役割を果たしていました。というのも、ガボンの人々は、誕生や結婚、病からの快気や成人式といった人生の節目節目に儀式を行っていましたから。館内でビデオをご覧いただければ、こうした古の文化をより深くご理解いただけるかと思います。
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
館内には現代美術を紹介するスペースもあり、現在はガボン出身のアーティスト、ミリアム・ミィンドゥの作品を紹介しています。彼女が写真や石けんの彫刻で造り上げた独創的な作品は、いかなる障害があろうとも(彼女の作品のように、例え両手を結び付けられ、縛られ、突き刺されても)、自由を求めて、芸術的な模索をした成果なのです。 |
 |
| |
|
|
 |
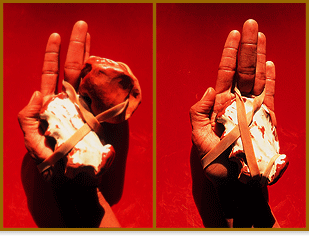 |
▲ミリアム・ミィンドゥ、シリーズ『Division plastique』
1999-2000, île de La Réunion
Photographies argentiques couleur. 24 x 36 mm
©ADAGP, Paris 2006. Courtesy Galerie Trafic, Ivry-sur-Seine |
  |
| |
|
|
|
 |
パリにいらっしゃる際には、是非、ダッペール美術館へ足を運んでみてくださいね。アフリカ美術発見への素晴らしいイントロダクションとなるような、興味深い展示にきっと出会えるはずですから。さらに、館内にある劇場や書店、そして静かな語らいにはぴったりの居心地のよいカフェをお訪ねになれば、この美術館が芸術作品、そして現代アーティストを迎え入れ、彼らと出会い、交流するにふさわしい、個性溢れる素晴らしい場であることがお分かりいただけるかと思います。
心をこめて。 |
 |
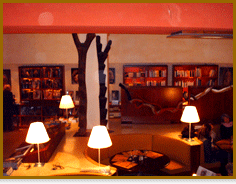 |
▲落ち着いた雰囲気のカフェ
©A.de Montalembert |
|
  |
| |
|
|
|
|
 |
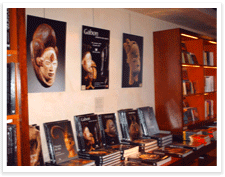 |
▲ 館内にある書店
©A.de Montalembert |
|
 |
 |
▲ポール・ヴァレリー通り
©A. de Montalembert |
|
 |
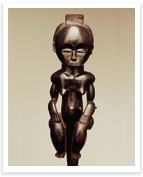 |
▲ファン族、聖遺物箱付属の像
Musée Dapper, Paris
©Archives Musée Dapper
photo Hughes Dubois. |
|
 |
|
 |
|