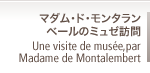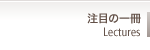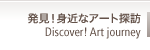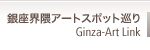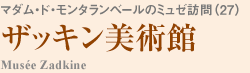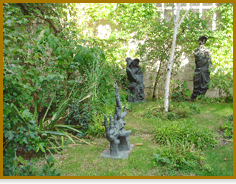 ▲奥=《大きなドレープのある顔》(1927年)
▲奥=《大きなドレープのある顔》(1927年)手前=《植物の手》(1957-58年)
©A.de Montalembert 緑の深く茂る美しい庭園に入るとすぐ、ザッキン芸術の世界が少しずつ現われてきます。1940年から1960年にかけて制作された壮大な彫刻作品が展示されたこの庭園をご覧になれば、ザッキンが自然に作品を溶け込ませた先駆者であったことがお分かりいただけると思います。左手にある力強い作品《破壊された都市のトルソー》(1947)はザッキンの代表作。1953年にオランダのロッテルダムに設置されたもので、第二次世界大戦の犠牲者へと捧げられたオマージュです。
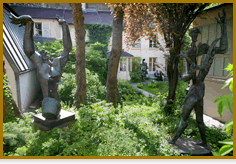 ▲左=《破壊された都市のトルソー》(1947年)
▲左=《破壊された都市のトルソー》(1947年)右=《オルフェ像》(1956年)
©Didier Messina ©ADAGP
少し先へ進むと、ザッキンが生涯にわたって取り付かれていた主題、ギリシャ神話の吟遊詩人《オルフェ像》(1956)があらわれます。この作品はなんと、二股の木片にインスピレーションを得て創られたものです。常に自らの芸術を追い求め続けたザッキンは、おそらく自らの仕事に本当に満足することは決してなかったのでしょう。
 ▲手前が《水を運ぶ女性》(1927年) ▲手前が《水を運ぶ女性》(1927年)©Didier Messina ©ADAGP |
 ▲右手奥が《人間の森》(1957-1958年) ▲右手奥が《人間の森》(1957-1958年)©A.de Montalembert |
さらに先へ進むと、《水を運ぶ女性》(1927)という作品が、厳かな佇まいで緑の中から浮かび上がります。ザッキンが大型作品を制作するために建てたアトリエのすぐ横にある、《人間の森》(1957-1958)という作品もお見逃しなく。人間と植物の融合というテーマのもと、ひとつとして同じ形のない作品が飾られています。 |
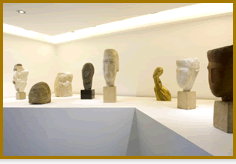 ▲ザッキン美術館の第1展示室。
▲ザッキン美術館の第1展示室。©André Morin
庭の奥には、19世紀に建てられた白い家があります。簡素な造りながら、小さな部屋が3つとベランダが1つ、ガラス張りの大きな部屋が1つ、そして大きなガラス壁のアトリエが2つあります。
美術館の経路に沿って進むと、時代を追って芸術家の作品を辿ることができます。
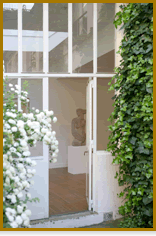 ▲窓の外から第3展示室を覗く。
▲窓の外から第3展示室を覗く。©Didier Messina ©ADAGP 最初の部屋は《人間の頭》という複数の彫刻作品にあてられていて、その多くは第一次世界大戦以前に作られたものです。こうした作品にはプリミティヴ・アートの影響が顕著に表れています。とりわけ、若い頃にロシアで制作した桃色花崗岩の《英雄の頭》(1911-1912)という作品には、ザッキンが自ら古代石工の継承者たろうとした決意がうかがえます。
セメントで作った《聖家族》(1912-1913頃)という作品は、絡まり合った人物像が集まったもので、その表現のやさしさと肉付きの穏やかさに、わたくしは感動を禁じえませんでした。お次の部屋では《扇を持つ女》(1923)と《アコーディオン奏者》(1924-1926)にご注目なさってください。主題をシンプルな幾何学的要素に分解するという、キュビスムの影響が見られるこの作品をご覧になれば、彼がいかにキュビスム運動に貢献したかがよくお分かりいただけるはずです。

▲ベランダに飾られた《金の鳥》(1926年頃)
©Didier Messina ©ADAGP
庭を望む小さなベランダには、おごそかでとても優美な《金の鳥》(1926頃)という作品が、あたかもこのミュゼに君臨し、そして護っているかのように飾られています。