
▲ピエール・ロティの家
©A.de Montalembert
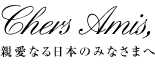
わたくしの夫の家族は、フランス南西部、太平洋に臨むシャラント=マリティーム県の出身で、18世紀以来、その地方のロシュフォールという町の近くに屋敷を所有していました。世界にその名を知られたリキュールの町コニャックの広がるシャラント川河口から、下流へと向うと、ロシュフォール。今回、皆さまをご案内するピエール・ロティの家のある小さな町です。

▲王室製綱所
©A.de Montalembert
この町が栄えたのは、17世紀以降のこと。ルイ14世(1638-1715)の宰相コルベール(1619-1683)によって重要な軍事工廠を備えた軍港が開かれ、以降、王室海軍の軍艦は、この港から遠く離れた目的地へ向けて出発したものでした。フランスの将軍ラファイエット(1757-1834)はイギリス軍と戦うため、1780年に部下を引き連れてここから船出し、米国へ向かいました。この工廠には王室製綱所(1666年)が置かれ、かつては王室海軍の大型帆船に使われた麻のロープが製造されていました。今も残るその建物の長さは374メートル、その壮大さと伝統的な美しさに、わたくしは驚かされるばかりでした。現在では国際海洋センターとなっているこの製綱所、皆さまもロシュフォールを訪れた際には、是非足を運んでみてくださいね。

▲ロシュフォールを流れるシャラント川
©A de Montalembert
わたくしと夫は、家族の出生の地を訪ねる機会にロシュフォールまで足を伸ばし、かの有名なフランスの旅行作家、ピエール・ロティ(1850-1923)の家を再訪いたしました。ロティの家は、ほかの家々に紛れておもわず見過ごしてしまいそうな、何の変哲もない小さな白い家。しかし、その内部へと一歩足を踏み入れれば、そこは、作家が少しずつ手を加え、さまざまな文化と時代を共存させた、とてもユニークですばらしい空間なのです。ロティが旅先から持ち帰った記念の品々からは、異国情緒を好んだ彼の好みが伺え、わたくしたちはあたかも、ロティと一緒に旅に出ているような錯覚におちいるほどです。この家はもともと、ロティの家族の住まいでした。彼はここで生まれ、生涯を通じて帰るべきただひとつの家だったのです。

▲デュプレ家の屋敷<ラ・リモワーズ>
©A.de Montalembert
ロティの本名はジュリアン・ヴィオー。ブルジョワのプロテスタントの家に生まれ、たいそう厳格な教育を受けて育ったようです。ふたつの大きな不幸が彼を襲ったのは、15歳のときでした。敬愛する兄を海で亡くし、親友リュセット・デュプレもまたこの世を去ったのです。デュプレ家の屋敷<ラ・リモワーズ>は、幼少期のロティが多くの時間を過ごした場所ですが、わたくしの夫の家族もまたデュプレ家とも深いつながりがあり、夫もよく訪れたそうです。
ロティは家族を助けるために海軍士官になります。そして1870年以降、彼はフランスから遠く離れた国々を旅するようになり、その際の経験をやがて多くの小説を発表することとなります。ロティとは熱帯の花の名で、1871年、タヒチでこのあだ名を用いたのがはじまりでした。そしてこのあだ名が1881年以降、作家としてのペンネームとなるのです。なかでも特筆すべきロティの旅といえば、1877年のトルコ滞在でしょう。緑色の瞳をもつ、若くすばらしい女性と出会い、熱烈な恋に落ちたロティは、そのトルコでの日々を綴り、小説『アジヤデ』(1879年)として発表。この作品によって一躍、有名作家となるのです。
後の『お菊さん』(1897年)という作品では、ロティが愛した長崎を思わせる町が舞台となっています。1885年、長崎を訪れたロティは、おかねさんという当時18歳の日本人女性と出会い、束の間の時間を夫婦のように過ごしましたが、その際の体験を語ったのが『お菊さん』です。ロティはこの作品を通じて、日本の洗練された文化と伝統を評価する自らの思いを綴りました。大きな話題を呼び、高く評価されたこの作品は、後にプッチーニ(1858-1924)の世界的に有名なオペラ『蝶々夫人』(1904年)の原案となったことでも知られています。
ロティは、作家としての名声を得て、財を成し、42歳でアカデミー・フランセーズの会員にも選ばれます。1923年に亡くなった際には国葬が営まれました。今はロシュフォールのほど近くにあるオレロン島に眠っています。






