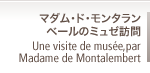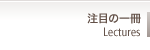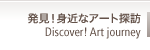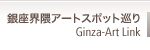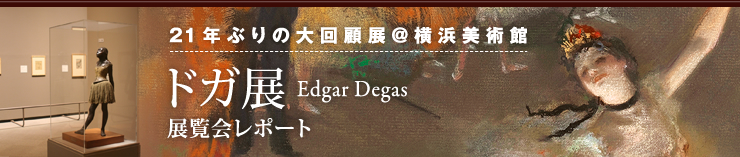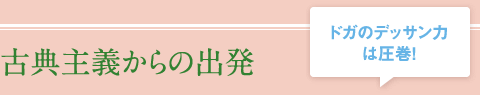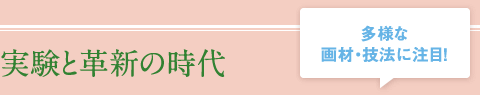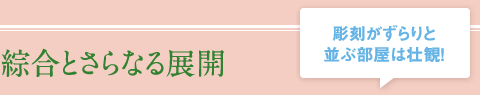「ドガにはいろいろな矛盾点があります」とソニエ氏は語りました。確かにドガは、外光表現を追い求めた印象派の中心的存在として君臨しつつも、自らはアトリエで制作。アカデミーには背を向けて、踊り子やその舞台裏、競馬といった斬新なテーマを扱いながら、新古典主義の巨匠アングルを崇拝し、その教えに忠実に従い、線描を重視しました。そして、ひと言では表現しづらくとも、ドガの作品には人を惹きつける強い力があるのもまた、事実です。その魅力はどこから来るのか──その答えを探して、MMFスタッフは21年ぶりのドガ大回顧展へ足を踏み入れました。
 ▲会場の入り口には、《エトワール》を再現した素敵な衣装がありました。
▲会場の入り口には、《エトワール》を再現した素敵な衣装がありました。 120点もの作品が集う今回のドガ展で、まず、私たちを迎えてくれるのは、ドガ21歳の自画像《画家の肖像》です。この絵が描かれた1855年、ドガはエコール・デ・ボザールに入学しました。尊敬する画家アングルの自画像を真似たポーズでこちらを見つめる若きドガは、冷ややかで不遜ともいえる表情をたたえ、自身が足を踏み入れた<芸術>という世界の正当性を確信しているかのようです。
 ▲エドガー・ドガ ≪画家の肖像≫ 1855年 オルセー美術館
▲エドガー・ドガ ≪画家の肖像≫ 1855年 オルセー美術館© RMN(Musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF-DNPartcom
Lewandowski/distributed by AMF-DNPartcom
<古典主義からの出発>と題された第一セクションで、何よりも驚かされたのは、歴史画《バビロンを建設するセミラミス》の習作として描かれた一連のデッサンです。その緻密で正確な描写力は、レオナルド・ダ・ヴィンチに匹敵するほど。「若者よ、線を描きなさい」というアングルの助言を熱心に支持したドガは、一枚の絵画を仕上げるまでに、ひとりひとりの登場人物の形態を完璧に描写しようと試みたのです。これを見ると、ソニエ氏がドガの特徴としてまず、「努力と根気」を挙げたことにも納得です。
また、このセクションでは、<競馬>をテーマとした作品がいくつか集められています。
エコール・デ・ボザールを早々に去り、歴史画のような古典的主題から、同時代の主題へ、ドガの興味が移行していったことがよく分かります。
 ▲エドガー・ドガ ≪バレエの授業≫ 1873-76年
▲エドガー・ドガ ≪バレエの授業≫ 1873-76年オルセー美術館
© RMN(Musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF-DNPartcom
1874年の第一回印象派展頃から1880年頃のドガに焦点を当てたこのセクションでは、今回の展覧会の目玉であるふたつの作品の美しさに目を奪われました。ひとつは油彩の《バレエの授業》。練習風景という臨場感溢れる作品でありながら、実際には、アトリエで踊り子たちにポーズを取らせて完成させたというから驚きです。そして、もうひとつは、今回初来日という傑作《エトワール》。会場ではライティングも素晴らしく、パステルならではの繊細な風合いがよく見てとれました。この幻想的な作品では、パステルのほかモノタイプ*という技法も用いられたそうです。
 ▲エドガー・ドガ ≪エトワール≫ 1876-77年
▲エドガー・ドガ ≪エトワール≫ 1876-77年 オルセー美術館
© RMN(Musée d'Orsay)/Hervé Lewandowski/distributed by AMF-DNPartcom
このセクションを一巡してみると、ドガが実に多様な画材・技法を用いていたことが一見してよく分かります。作品を見る際には、画材と技法にぜひ注目してみてください。油彩やパステルのほか、版画でもアクアチントやエッチング、リトグラフ、ドライポイントとさまざまな技法の名が記されています。そのことひとつをとっても、ドガが自らの表現を求めて、常に実験を繰り返していたことが伺えます。
モノタイプ*金属板にインクで描いた図柄を紙に刷りとる技法。
 ▲バックの黒もライティングも、《エトワール》にぴったりでした。
▲バックの黒もライティングも、《エトワール》にぴったりでした。  ▲セクションとセクションの間には、ドガの詩をあしらったパネルも。
▲セクションとセクションの間には、ドガの詩をあしらったパネルも。  ▲<浴女>にまつわる作品がずらりと並びます。
▲<浴女>にまつわる作品がずらりと並びます。 1880年以降の作品が集うこのセクションでは、油絵は数えるほどで、ほとんどの絵画作品がパステルで描かれています。パステルは溶液を用いないので素早く描け、目を近づけて制作できるので、視力の衰えていったドガにとって欠かせない画材だったといいます。
 ▲エドガー・ドガ ≪浴後(身体を拭く裸婦(複製)≫ 1896年頃 フィラデルフィア美術館
▲エドガー・ドガ ≪浴後(身体を拭く裸婦(複製)≫ 1896年頃 フィラデルフィア美術館Courtesy of the Philadelphia Museum of Art
その多くが《浴盤(湯浴みする女)》をはじめ、<浴女>をテーマとした作品です。ずらりと並んだこれらの作品群を見てから、改めて初期のデッサンを思い出してみると、その単純化された表現に驚かされます。画面を暖色で満たした《浴後(身体を拭く裸婦)》などは、もはや抽象画に近いような印象さえあります。ドガ自らが撮影した同じポーズの裸婦の写真が並べて展示されているのも、ドガと写真との関係を示していて、興味を引かれました。
そして、圧巻は最後の部屋です。さまざまなポーズをとった踊り子や馬などの彫刻がずらりと並んだ様子は、あたかも、その死後に150点もの未発表彫刻の塑像が発見されたというドガのアトリエのようでした。
 ▲アトリエで発見された塑像は、ドガの死後、鋳造されたそうです。
▲アトリエで発見された塑像は、ドガの死後、鋳造されたそうです。 確かなデッサン力を示した若き日々、新たな主題に挑戦して芸術を革新した円熟期、そして視力を失いながらもなおも新しい表現法を模索し続けた晩年──。120点もの傑作が集う今回の回顧展では、ソニエ氏が語ったように<努力>の末に生まれたドガ芸術の軌跡を丁寧に追うことができました。そして、完成作には<努力>の跡をみじんも残さない、そこに、“ダンディー”と称された生粋のパリジャン、ドガらしい美学を感じました。
- 会期
2010年9月18日(土)〜12月31日(金) - 会場
横浜美術館 - 所在地
横浜市西区みなとみらい3-4-1 - Tel
03-5777-8600(ハローダイヤル) - URL
美術館
http://www.yaf.or.jp/yma/
- 開館時間
10:00-18:00
金曜日は20:00まで
*入館は閉館の30分前まで - 休館日
木曜日
*ただし9/23、12/23、12/30は開館 - 入館料
一般:1500円
高校・大学生:1200円
中学生:600円
小学生以下:無料
*毎週土曜日は高校生以下無料
*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。