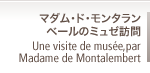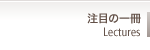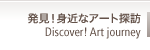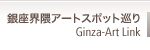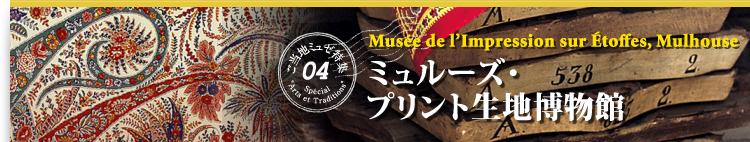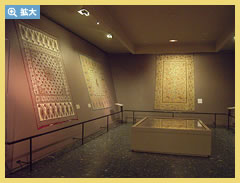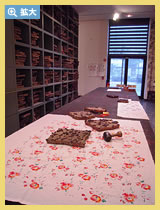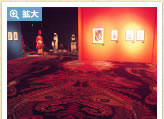博物館のイントロダクションとなる最初の展示室には、世界各地のさまざまな染色製品が集められています。インドネシアの伝統的なろうけつ染めのバティック(Batik)、田園風景を銅版のローラーで印刷したフランスの有名なトワル・ド・ジュイ(Toile de Jouy)、日本の型紙を使用した染物、そしてスクリーンプリントによる有名ブランドのスカーフと、国も時代も技術も異なる染色製品が一堂に会しています。モチーフや風合いなど、それぞれの特徴を比較しながら楽しむことができる魅力的な展示です。
続くふたつ目の展示室を飾るのは、ヨーロッパのプリント生地産業の原点ともいえる、インド更紗の貴重なコレクションです。水洗いをしても柄がにじまないプリント生地の基本の技術は、このインド更紗によってヨーロッパにもたらされました。ここでは繊維に色を固着させる金属の媒染剤についても紹介されています。またインド更紗は、技術はもとより、その模様もヨーロッパのプリント生地産業に大きく影響を与えました。インド更紗の魅力はなんといっても布地を覆いつくすような唐草模様とその鮮やかな色彩にあります。展示されている数百年も前のインド更紗が、今もなおその色彩を留めているのがとても印象的です。
世界各地のプリント生地の魅力を堪能した後は、ミュルーズのテキスタイル産業の歴史やプリント生地の技術を語る展示が続きます。媒染剤を使用した染色の工程を分かりやすく説明する模型や、伝統的な印刷の過程で使われる木版、デザイン画の展示など、18世紀の染色作業の主要なステップが紹介されています。さらに博物館の2階では、伝統的な印刷技術とは対照的な、機械による印刷技術の展示を見ることができます。19世紀初頭に造られた複数のローラーを使用した大型の機械の展示をメインに、下絵のデザインや版画製作のための道具など、機械化されたプリント生地製造のひと通りの作業過程が見て取れる内容です。
こうした展示を順に見ていくと、技術が進歩してもなお、デザイン、染料の配合、布地への印刷と、染色の作業過程には変わらず専門の職人が存在し、それぞれが重要な役目を担っているということに気付かされます。
そして、ミュルーズ・プリント生地博物館の最後を締めくくるのは、博物館が年に1〜2回行っている企画展の展示です。布製品はたいへん傷みやすいため、博物館の膨大なテキスタイルのコレクションは、ほとんどの場合、企画展を通してしか鑑賞することができません。
そうした理由からも博物館を訪れる際には、ぜひじっくりと時間をかけて鑑賞したいセクションです。2011年4月より始まるのが、フランスのオート・クチュールをテーマにした、ドイツ人写真家のウィリー・メイワルド(Willy Maywald)の写真展です。この企画展では写真とともに博物館の貴重なオート・クチュールのコレクションも公開されるということです。また2年後の2013年にはパリのギメ美術館とのコラボレーションによる、日本の伝統的な染色技術である「筒がき」の展覧会が行われる予定です。
[FIN]
- 所在地
14, rue Jean-Jacques Henner-BP 1468-68072 Mulhouse cedex - Tel
+33(0)3 89 46 83 00 - Fax
+33(0)3 89 46 83 10 - URL
http://www.musee-impression.com - 開館時間
10:00-12:00、14:00-18:00
*12月の毎週月曜日は午後のみ特別に開館 - 休館日
月曜日、1月1日、5月1日、12月25日 - 入館料
一般:7ユーロ
割引料金:3.5ユーロ
12〜18歳:3ユーロ
- B1Fインフォメーション・センターでは、ミュルーズ・プリント生地博物館の関連書籍を閲覧いただけます。
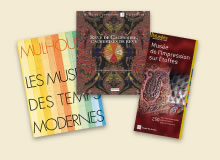
*情報はMMMwebサイト更新時のものです。予告なく変更となる場合がございます。詳細は観光局ホームページ等でご確認いただくか、MMMにご来館の上おたずねください。